米油のデメリットや疑問点 /「サラダ油との違い」「玄米を食べれば米油はいらない?」など
更新:

「米油」という名を聞くと、「お米から油が抽出できるものなの?お米って、油っぽいイメージが全然ないんだけど」と、イメージ的に疑問を持つ人も多いでしょう。
確かに、白米に含まれている油分は、0.3%程度という、非常に少ない数値となっていますので、ここから油を抽出できるとは思えませんよね。
ですが、実は米油は、白いお米ではなく、「米ぬか」から抽出される油なのです。
米ぬかには約20%の油分が含まれており、これが米油として使われるんですよ。
そんな米油の大きなメリットとして挙げられるのは、以下の3点。
- 国産の米ぬかを原料としている米油がほとんどで、安心感が高い。
- 古来より米を食べてきた日本人にとって米油は非常に相性が良く、おいしいと感じられる。
- 油分だけでなく、米ぬかに含まれている豊富な栄養も含まれている。
食卓で使う油のラインナップに米油を加えれば、それだけで日々の料理のおいしさもアップ!同じ食材を使った料理でも、より高い満足感を得ることができます。
[目次]
米油のデメリットや利用する時の注意点
米油は加熱に強いため、炒め物や揚げ物にも使えるなど、調理の幅が広くて使いやすいのが大きな強みと言えますが、ちょっとしたデメリットや、注意点などもあります。
デメリット(1)寒い季節は使いづらい!?
米油の弱点として挙げられるのは「加熱に強い反面、寒くなると硬くなってしまうこともある」ということです。
サラダ油の原料として使われるなたね油やコーン油・ひまわり油などは、融点が−10℃クラスまたはそれ以下なので硬くなりにくいのですが、米油の融点(固体が液体になりはじめる温度)は、−5℃程度。これは、ごま油と似たレベルの融点です。
ごま油を使ったことがある人なら、一度は「冬の寒い日に、ごま油が硬くなって、出にくくなって困った」という経験をしたことがあるのではないでしょうか。米油使用に際しても、それと同じような現象が起こるのです。
デメリット(2)米油のパワーは圧搾製法でないと生かせない!
米油利用の際の注意点として挙げられるのは、「米油に含まれる成分による健康・美容作用の恩恵を受けたいなら、圧搾製法で抽出されたものを選ぶ必要がある」ということです。
米油の抽出法としては、「米ぬかを機械で物理的に押しつぶすようにして油を搾りだす圧搾製法」と、「化学溶剤などを米ぬかに混ぜて油分を溶かしだして抽出する溶剤抽出法」があるのですが、この2つの製法の油の質を比べると、圧搾製法のほうが断然上です。
なぜなら、溶剤抽出法は、その抽出・精製の過程において、油分に含まれているせっかくの成分が減少・分解してしまうのです。
米油の成分の中で最も注目されている万能成分・γ-オリザノールの含有量も、溶剤抽出法で作った米油のγ-オリザノール含有量は、圧搾製法の米油に比べて非常に少ないのです。
たとえば、圧搾製法の米油の中でも特にγ-オリザノール含有量が多いことで人気のコメーユと一般的な溶剤抽出法の米油とを比べると、約8倍もの含有量の差があるほどです。
さらに、トコトリエノールや植物ステロールの含有量も、圧搾製法の方が数割程度高い、という状態になっています。
価格としては、同じ量の米ぬかでも圧搾製法より多くの油が抽出できる溶剤抽出法の米油のほうが安いので、「とにかく価格重視」という人は溶剤抽出法の米油を選ぶのもやむを得ませんが、質を重視、成分の恩恵の度合いを重視したい人は圧搾製法の米油を選ぶようにしましょう。
米油と一般的なサラダ油、どこが違う?
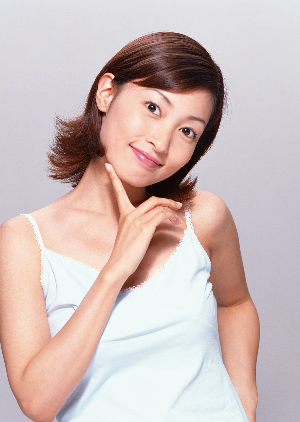
私たち日本人が、料理でよく使う油の代表格が「サラダ油」です。
そんなおなじみのサラダ油と、米ぬかから摂れる米油って、何が違うと思いますか?
成分面では圧倒的に米油が有利!
一般的なサラダ油と米油を比べると、健康・美容に役立つ成分の充実性を見れば圧倒的に米油が有利と言えます。
米油には、オレイン酸・必須脂肪酸のひとつリノール酸・ビタミンEやトコトリエノールが含まれています。さらに、γ-オリザノールまで含まれているのが最大の強み。
γ-オリザノールは米ぬか由来のポリフェノールなので、普通のサラダ油には、この成分の恩恵は期待できないのです。
価格面と入手しやすさではサラダ油が有利!
サラダ油が有利な点はやはり「米油よりずっと安価で買える」ということ、そして「どんなスーパーにでも売っている」という、価格と入手しやすさの2点ですね。
米油は、「米ぬか」から作られる油なので、あまり不足しなさそうなイメージがありますが、実はちょくちょく不足問題が起きるのです。 日本人の米の消費量が昔に比べて減った分、できる米ぬかの量も、昔より減っているのです。
サラダ油より高いし、供給量もやや不安定、ということで、米油を取り扱っていないスーパーも少なくありません。
味の比較は?
では最後に、料理に使う油として、米油とサラダ油の味を比べてみるとどうなのかというと…
米油のほうが、「さっぱりしていて胃もたれしにくい、揚げ物もカラッと揚がる」という声が多いです。ですから、米油を使っての料理は食べやすく、多くの人に好まれやすいと言えるでしょう。
ですが逆に、「こってりしていて、少々クドく感じるぐらいの料理がいい」という人にとっては、サラダ油の方が好みかもしれませんね。
玄米を食べれば米油はいらない?

米油は、「米ぬか」から摂れる油ですが、それを聞くと「じゃあ、米ぬかたっぷりの玄米を食べていれば、別に米油を使わなくても、同じ効果が得られるのでは?」と考えちゃいますよね。その疑問にここでお答えします!
玄米を食べて米油摂取の代わりにするのは難しい
玄米を食べれば米油はいらないのか?その答えは「NO」です。
なぜなら、「玄米を食べるだけで、じゅうぶんな量の米油を摂るのは難しい」という理由があるからです。
具体的に、数値でご説明しましょう。
まず、玄米1合は約150g。これを精米すると、白米が9割で、残り1割が米ぬかとなります。
つまり、1合の玄米についている米ぬかの量は15g。
そして、米ぬかに含まれている油分は約20%ですから、1合の玄米についている15gの米ぬかから摂れる油分は、約3g、という計算になるんですよ。
これに対し、米油の1日の摂取目安量は大さじ1杯、約14g。
そう、なんと、玄米だけで米油を摂ろうとすると、1日あたり5合近くも食べなければ、14gの目安量に到達しないのです。
よほどハードな仕事やスポーツをして、多大なカロリーを必要とする人でもない限り、「1日5合近くの玄米を食べる」というのは、どう考えても食べすぎですよね。
玄米を食べても米油の吸収率が悪い!?
「玄米を食べれば米油はいらない」説がNOである理由は、もうひとつ。「玄米の消化の悪さ」も問題となってきます。
玄米は、食物繊維豊富な薄皮で覆われていますが、この薄皮をきちんと噛み砕かないと、玄米の栄養分をしっかり消化することはできません。
玄米を食べても、ほとんどの人は「噛み不足」となり、せっかくの米ぬかの栄養をちゃんと生かしきれない、という感じになりがちなんですよね。当然ながら、米ぬかに含まれる油分についても、「よほどよく噛んで、薄皮の影響を残さないようにしないと、ちゃんと消化しきれない」という状態になります。
ですから、たとえ玄米5合近くを食べたとしても、消化吸収の効率まで考えると、「米油大さじ1杯を摂取するのと同じ」とは言えないのです。
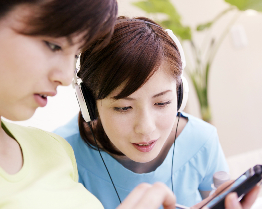
■ サラダオイル特集
