えごま油の選び方、調理での使い方、アマニ油との違い、デメリットなど
更新:

えごま油というと、「ごま油と一文字しか違わないから、ゴマ科の植物から摂れるのでは」と思っている人も多いですが、そうではなく、えごまはシソ科の一種となります。
見た目は青じそに似た感じなのですが、このえごまの種子から抽出されるえごま油は、まさに「特別な油」。今話題のオメガ3系脂肪酸が、たっぷり含まれているのです。
ここでは、そんなえごま油のメリットや摂り方、えごま油と並んで人気の亜麻仁油との比較、さらにえごま油の選び方のコツなどをお伝えします。
[目次]
「えごま油」と「アマニ油」の違い
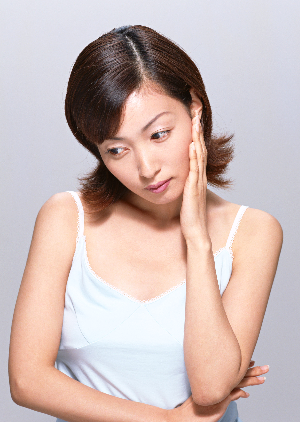
オメガ3系脂肪酸であるα-リノレン酸が豊富に含まれる食用油の中で、特に人気が高いのが、えごま油と亜麻仁油です。
この2つの油、どちらがいいのか?徹底比較してみましょう!
熱・光に対する弱さと味については互角!?
えごま油も亜麻仁油も、熱や光に弱く、酸化しやすい、と言うデメリットがあるのは同じです。開封した後は冷蔵庫保管をして、1〜2ヵ月程度で使い切ることが必要です。
あと、味については、どちらも少し生臭い感じの独特の風味があり、大差はありません。
価格とα-リノレン酸含有量はえごま油に軍配!
えごま油と亜麻仁油の価格を比べると、全体的には「えごま油のほうが、亜麻仁油よりも2〜3割程度安い価格で買えるものが多い」という感じです。
また、α-リノレン酸含有量についても、えごま油は60%前後、亜麻仁油は50%前後という状態となっているため、「同じ量を摂取して、より多くのα-リノレン酸が摂れるのはえごま油」ということになります。
容器の質は亜麻仁油に軍配!
えごま油・亜麻仁油ともに「光が当たると酸化・変質しやすい」という弱点があるため、容器は遮光性にすぐれたものが好ましいのですが、この点で比較すると、「遮光性の容器を使っているケースが多いのは亜麻仁油のほう」という傾向が強いです。
えごま油は「ビンには遮光性がなく、箱で遮光している」という商品の割合が多いんですよ。何も知らずに箱を捨ててしまう、というのはよくある話ですから、やはり、ビンなど「油が入っている容器そのものの遮光」がなされているほうが好ましいんですよね。この点は亜麻仁油が有利と言えます。
産地の安心感では亜麻仁油に軍配!
亜麻仁油の原産地はその大半がカナダおよび北米で、「海外の産地としては、比較的安全性が高い部類」に入ります。/p>
これに対し、えごま油はほとんどが中国産。「中国産食品にどうしても不安がある」という人には、手が出しにくい油と言えるでしょう。
ですから原産地に対する心理的安心感についても、亜麻仁油に軍配が上がります。
えごま油と亜麻仁油の比較まとめ
- えごま油のほうが、価格が手ごろ
- えごま油のほうが、α-リノレン酸の含有率が高い
- 容器の遮光性は亜麻仁油のほうがすぐれているケースが多い
- 産地の安全性イメージなどは亜麻仁油のほうがすぐれているケースが多い
安く効率よくα-リノレン酸を摂ることを重視するか、酸化・変質リスクの低さや安全性を重視するか、それによって選ぶ油が違ってくる、といったところですね。
えごま油の正しい選び方
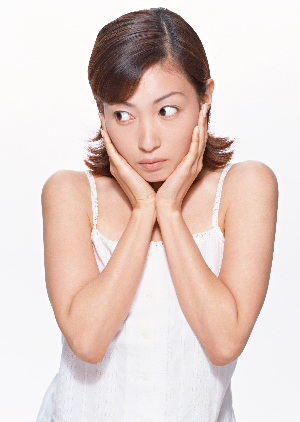
えごま油は、健康番組などのおかげもあって近年認知度が高まり、スーパーなどでも複数のえごま油が販売されているなど、商品の選択肢が幅広くなっています。
それはありがたいのですが、数多くのえごま油の中から、どういう点を見て選べばいいのでしょうか?そのポイントを説明します。
えごま油は、低温圧搾法で抽出されたものを選ぼう
えごま油選びで一番重視すべきポイントは、「低温圧搾法(コールドプレス製法)で油を抽出しているかどうか」という点です。
低温圧搾法は、「えごま種子を物理的に押しつぶして油を抽出する」という抽出法で、人工的な加工とは違う、安心な抽出法と言えます。
しかし、低温圧搾・コールドプレスなどの記述がどこにもないえごま油は、「油を溶剤抽出している」という可能性が高いです。
溶剤抽出法は、同じ量の原料から摂れる油の量は低温圧搾法よりも圧倒的に多いというメリットはあるものの、抽出工程で薬品を使うだけでなく加熱もされてしまうため、えごま油は大きく変質してしまいます。
その結果、酸化・変質してしまうリスクさえあるのです。ですから「溶剤抽出かもしれないえごま油」を選ぶことは、絶対におすすめできません。
えごま油は国産とまぎらわしい海外産があるので注意!
「一見、国産えごま油のように見えて、実は原料のえごまが中国産だった」など、海外産を間違って買ってしまうケースも少なくありません。
なぜ、そんなことが起こるのかというと「国内製造」や「日本国内充填」「国内製油「加工地:日本」など、たとえ原料のえごまは中国などから輸入していても、えごま油にする過程を国内でおこなったものが、いかにも国産っぽい表記で販売されているケースも多いからです。
間違って買ってしまわないためには、「〇〇県産のえごま100%使用」など、えごま自体が本当に国内産のものであるという趣旨の表記があるものを選びましょう。
「色の濃いえごま油のほうがいい」わけではない!
えごま油選びの際に「色が濃いほうが、成分も濃くていいえごま油」と考える人も居ますが、実はその選び方はアテにはなりません。
2016年1月の、国民生活センターによる、えごま油に関する報道発表資料の中で、「えごま油の色からは、脂肪酸組成の違いは分からない」という趣旨の記述があります。
それどころかむしろ「焙煎したものや圧搾時に高温になったものは茶褐色が濃くなる傾向がある」という趣旨の記述があるほど。
えごま油の熱への弱さを考えると、むしろ、色があまりに濃いものを選ぶことは、リスクが高い可能性があると言えるのです。
「脂肪酸組成がおかしい、怪しいえごま油」をつかまされないためには、「メーカーホームページあるいはパッケージのどこかに、α-リノレン酸量の表記があるものを選ぶ」というのがおすすめです。
α-リノレン酸の含有率の表記でもいいですし、「小さじ1杯あたり、α-リノレン酸〇g」などという表記でもかまいません。要は「α-リノレン酸がどれだけ含まれているかを何らかの形で表記している」ということが重要なのです。
えごま油のデメリット
えごま油は酸化しやすい!遮光できることも絶対条件
えごま油は、熱だけでなく光によっても酸化・変質してしまいやすいという大きなデメリットがあります。
だからこそ「透明のビン入りで、箱にも入っていないえごま油」は、絶対に選ぶべきではありません。
一番の理想は、「遮光ビン+箱が使われている」というもの。それが無理でも、せめてビンか箱のいずれかで遮光がなされているものを選びましょう。
国産えごま油が高すぎる
現在市場に出回っているえごま油は、その大半が中国産。次に多いのが韓国産で、国産えごま油というのはかなり貴重な存在です。
貴重だからこそ、「国産えごま油を見つけたら買いたい」という人も多いでしょうが、国産えごま油には、価格が高いというデメリットがあります。
中国産の手ごろなえごま油と比べると、国産えごま油の価格は数倍もしくはそれ以上という、かなりの高額となっているものがほとんど。
えごま油は、同じくα-リノレン酸豊富な亜麻仁油と比べると数割程度安価なのがメリットのひとつとなっているのですが、国産えごま油では、そうした価格面のメリットはまったく得られないわけです。
えごま油の摂り方・調理での使い方
えごま油は、「ヘタに加熱すると、せっかくのα-リノレン酸が過酸化脂質化してしまい、かえって体に悪い状態になってしまう」という弱点を持っているため、炒め物などの調理には使えません。
サラダや冷奴にかけたり、「ある程度温度が下がった状態(60℃以下)の炒め物や煮物にかける」という形で摂取するのが基本です。
スプーンにえごま油をすくって、そのまま食べようとする人もいますが、えごま油は少し生臭い感じの風味があるため、これを続けると「えごま油の風味が嫌いで、もう食べたくない」という状況になりやすいのでおすすめできません。
さらに、「えごま油をそのまま食べるのは、食べ物と一緒にえごま油を摂取するケースと比べると、消化効率が悪くなってしまう」というデメリットもあります。 えごま油がいくら健康的な油と言っても、「油オンリーを胃に注ぐ」というのは、さすがに負担となってしまうのです。
えごま油の手軽な摂り方
えごま油の手軽な摂り方としては「えごま油サプリを飲む」という手もあります。
サプリはカプセルが小さいので、えごま油の摂取量としては少なめになってしまますが、「今日は外食で、さすがに外食にえごま油はかけられない」という日などに使うのはおすすめです。
アルミパウチなど、しっかり遮光された良質なサプリを選び、食後に飲むといいでしょう。
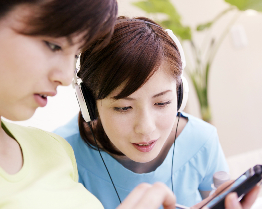
■ サラダオイル特集
